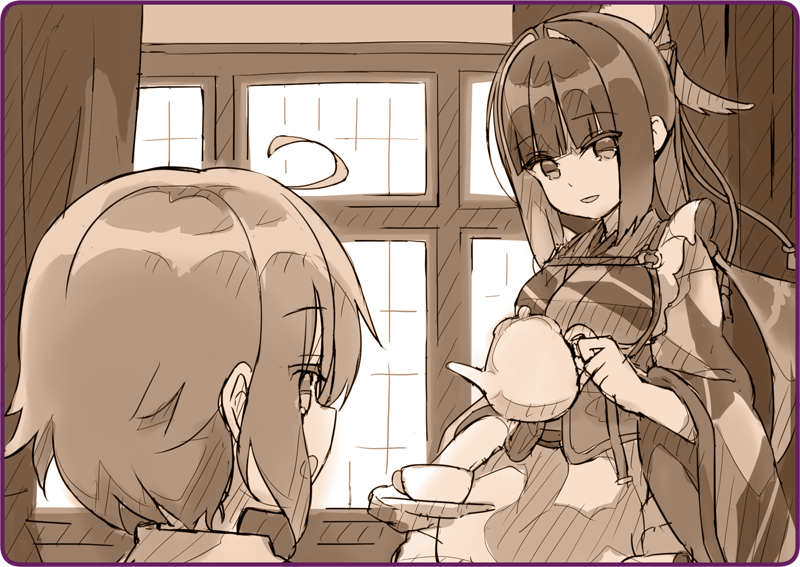一昼夜が経って。
ぐるぐると鍋をかき混ぜながら、あたしはひとりごちた。中身は干し鱈と玉葱、じゃがいもだ。ヘレナ島の冬では定番料理……というよりも、これ以外食材がないというほうが正しい。皇国風の味付けにしたかったところだが、醤油の一瓶も手に入らないので諦めざるを得なかった。
戦闘人形失格と言わざるを得ない。故障することはいままでも多々あったが、直るかどうか分からない不具合を抱えるのは初めてだ。もしかすると、だから論理機関が不安定になったのかもしれない……。
不意に、控えめなノックの音が響いた。
確か、朝方いつもの調子で起きだしてきて、身支度もそこそこにどこかへ出かけたはずだ。いつもそんな調子で、どこでなにをしているのか、鴉羽も分からないことが多い。
いつもは帰宅してもノックなんてしないくせに、今日はなにやら遠慮がちだ。どうしてだろうと考えて、はたと気がついた。
あり得る。今夜は皇軍のお客様がいらっしゃるというのに、また機械いじりでもしていたのだろうか。慌ててエプロンで手を拭うと、玄関に駆けだした。
女の子「きゃっ!?」
ローサ「あ、あの……こんにちは」
どうやら、勘違いだったようだ。
ローサ「あははは……いいの。あの、これ、お爺ちゃんが持っていってって…」
そういって、胸に抱えている麻袋を差し出してくれる。
中を見ると、丁寧に凧糸で縛られた、鮭の切り身の燻製が入っている。
ローサ「昨日はお手伝いしてくれて、ありがとう」
ローサ「ううん、お礼だから」
燻製を受け取る。春が近いとは言え、まだまだ外は寒い。少女の鼻先はすっかり赤くなっていた。
ローサ「え?」
* * *
ローサを暖炉の前に座らせる。
ローサ「わ、おいしそう」
以前マスターからもらったローズヒップの実。持てあましていたので、蜂蜜で煮てジャムにしておいたのだ。
ローサ「じゃあ、一緒に食べよう?」
ローサ「食べられないの?」
ビスケット一枚にジャムをのせて、それぞれ頬張る。
ローサ「甘酸っぱくておいしー……」
真っ赤なほっぺを膨らませて、嬉しそうに笑っていた。
ローサ「鴉羽さんは、このお家でメイドしているんだ」
ローサ「ごめんなさい」
ローサ「最初会ったとき、ひどいことを言って。てっきり皇国の戦闘人形かと思って……」
ローサ「わたし、戦闘人形が嫌いだから」
不意に漏らしたのは、冷たい言葉だった。
ローサ「ううん、わたしたちを守ってくれないから」
カップの水面を眺めながら言葉を濁す。なにか話したくない記憶があるのかもしれない。
ローサ「お爺ちゃんちに疎開しにきたの。もう何年も前に」
ローサ「皇軍の人形たちがやってきて……わたしの街を占領して……でもそれなのに、ローベリア軍が攻めてきたとき……あの人たちはわたしたちを守ってなんてくれなかった。それどころか……」
ぽたりと水面が揺らぐ。
ローサの涙だった。
ローサ「う……うっ……」
感情を堪えきれない様子で、ぽろぽろと涙を流している。
いったいどうすればいいのかと、鴉羽は迷った。こんな時人間ならば……マスターなら、どうしただろうと。
そっと、その肩を撫でた。
ローサ「鴉羽さんっ……」
その反応は意外なものだった。
少女は鴉羽の胸元に顔を埋めて、さめざめと泣き始めていた。
なにが大丈夫なのか、分からない。
それでも、鴉羽はそうし続けていた。